内容は戦争中の出来事なのですが、そういうこととは別に、文体というか、文章のスタイルというものの個性がよくわかる英文で、単語や文法、文章の意味がわかっても、この独特のリズムのようなものを日本語にするとどうなるんだろう?という、翻訳の難しさというか、制約と自由を体感できる翻訳体験でした。
ヘミングウェイの短編は、新潮文庫の『ヘミングウェイ全短編(高見浩訳、全3巻)』が好きで読みふけったことがありますが、『翻訳教室』のように、複数の訳を比べる愉しみを知ってしまうと、単に日本語だけなんてもったいないという気持ちになってきます。それにヘミングウェイを訳すのって翻訳初心者のわたしにはいい課題になるかもと、まずは、柴田元幸訳の『こころ朗らなれ、誰もみな』を入手。原文は、"The Complete Short Stories of Earnest Hemingway, the Finca Vigía Edition"を使うことにして、と『翻訳教室』が終わってからの課題をただいま準備中。
それにしても、ヘミングウェイの短編ていろんな人が訳してて、そのこと自体も面白いです。原文読んで、翻訳読んで、「いや、自分だったらこうは訳さないよ」と工夫してみたくなっちゃう、そんな魅力があるんじゃないかしらん?
ちなみにわたくし、大学に入ってすぐの英文の授業の課題は、『老人と海』の英訳でした。当時は「なんで既に訳が出版されてる人の文章を英訳されるんだろう?意味ないじゃん」とか「魚用語が多すぎるよ、難しいよ」と、あまり真面目に取り組みませんでしたけど、今になってみると、受験英語の後にヘミングウェイを読ませてくれた英文の先生に感謝です。


 われらの時代・男だけの世界 (新潮文庫―ヘミングウェイ全短編) 高見浩訳
われらの時代・男だけの世界 (新潮文庫―ヘミングウェイ全短編) 高見浩訳 勝者に報酬はない・キリマンジャロの雪―ヘミングウェイ全短編〈2〉 (新潮文庫) 高見浩訳
勝者に報酬はない・キリマンジャロの雪―ヘミングウェイ全短編〈2〉 (新潮文庫) 高見浩訳 蝶々と戦車・何を見ても何かを思いだす―ヘミングウェイ全短編〈3〉 (新潮文庫) 高見浩訳
蝶々と戦車・何を見ても何かを思いだす―ヘミングウェイ全短編〈3〉 (新潮文庫) 高見浩訳 こころ朗らなれ、誰もみな (柴田元幸翻訳叢書)
こころ朗らなれ、誰もみな (柴田元幸翻訳叢書)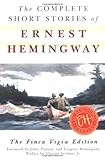 The Complete Short Stories Of Ernest Hemingway: The Finca Vigia Edition
The Complete Short Stories Of Ernest Hemingway: The Finca Vigia Edition






