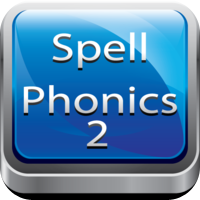英会話も日本語で考えて英語にしよう、なんて思ってるうちはあんまりしゃべれなくて、日→英の回路というんでしょうか、日本語で考えて英語に直すっていうのを全くあきらめて、英語で物事を体験して、英語を聴き、英語を話す、っていう風に、英語な体験を重ねていくうちに、ある程度は話せるようになりましたし、英語でメールとか論文とか、書く方もできるようにすこしずつなっていきました。
しかしそれでもなお苦手だったのが、日本語と英語をいったりきたりすることで、自分で書いた日本語の小説をオーストラリア人の友達に手伝ってもらいながら英語に書き直してみたら、まったく別の小説になってしまう、だとか、英語で書いた論文を、博士論文の中にいれるために、日本語に直す、という作業をしようとしたら、内容は世界中の誰よりもわかってるはずだったのに(!)なかなか日本語になおせず苦労しました。
とまあ、翻訳が苦手なわたしは、翻訳文学も大人になってからはそんなに読まなかったのですが、唯一すうっと読めて大好きになった翻訳家さんと作家さんがいて、それは柴田元幸さん訳のポール・オースター(Paul Auster)の作品群でした。
オースターの小説は当時バイトしてた図書館にずらっと並んでいたので、順にどんどん借りて読んでリクエストもして(職権乱用?笑)『孤独の発明(The Invention of Solitude)』、『シティ・オブ・グラス(City of Glass)』、『幽霊たち(Ghosts)』『鍵のかかった部屋(The Locked Room)』、『最後の物たちの国で(In The Country of Last Things)』『ムーン・パレス(Moon Palace)』『偶然の音楽(The Music of Chance)』『リヴァイアサン(Leviathan)』と読んでいったところ、同じオースター作品でも何か明らかに違っていたのが、『シティ・オブ・グラス』で、なんで?とあらためて翻訳者の名前を確認すると、この本だけが、柴田元幸さんじゃない人の翻訳で、ここではじめてわたしは、翻訳者という裏方的なお仕事のチカラというか、影響力を感じたのでした(現在では柴田元幸訳で『ガラスの街』という本が出ています)。
そんな「翻訳家さんてすごいんだ!」と感じさせてくれた柴田元幸さんが新しい雑誌「MONKEY」を創刊、しかも特集は「青春のポール・オースター」(!)と知り早速入手。大事に読もう、オースターはわたしにとっても青春だあ、と思っていた矢先に、友達からのメールで、柴田元幸さんが絵本作家のきたむらさとしという人と金沢でトークショーをする!と知り、もううっきゃーな感じで、行ってきたのが先週の日曜日のこと。
トークショーは柴田さんによるきたむらさとし氏の作品紹介にはじまり、翻訳と文章から絵を描くことを比較するようなお話、柴田さんが物語を朗読して、きたむらさんが即興で絵を描き、その次は別の話を柴田さんが朗読して、参加者全員が絵を描き、それを最後に講評して、というなかなか刺激的な2時間でした。
トークの中で印象に残ったのは、柴田さんがいい翻訳、だと思うのは「いろんな読みの可能性をじゃましない訳」「多岐的な訳」「ニュートラルな訳」だ、という言葉でした。で、質疑応答の時間に、そういう翻訳をするには、どういう心構えでいたらいいのか、と質問してみたところ、「翻訳はボトムアップな仕事であり、何も考えない訳がいい。そのためには、文法的知識が必要」というような答えが返ってきました。
「無心」って、とても職人チック。そして今のわたしは英語を訳そうとすると、文法はもちろん、単語の意味もあーでもない、こーでもないと考えてしまうのですが、それってまだまだ翻訳の基礎体力がないってことなんだろうなあ、と理解。
そして、トーク後のサイン会には『翻訳教室』と『Monkey』を手にもって、どっちにサインしてもらおうか迷いながら臨んだところ、『Monkey』を見た柴田さんはなんだか嬉しそうで、かわいいサインをしてくれた後に、「誤植があるんだ」とぱぱっとp.30を開いて「<い」と書き込み、唖然とするわたしをみて、「乾くまで時間がかかるからね」とひとこと。
翻訳職人、なれるものならなってみたいです。そのためにも、言葉の基礎体力、しっかりつけよう。
東大の授業を書籍化したまさに「翻訳教室」体験ができる本。難しすぎて真ん中ぐらいで止まってしまってましたが、サインもいただいたことだし、がんばりたいと思います。ちなみに、柴田さんに「難しすぎます」と言ったら「すいません」と謝られました。笑